
機械材料の基礎:鋳鉄
鋳鉄とは
鋳鉄は、鉄を主成分とし、炭素を多く含む鉄-炭素系の合金です。炭素量がこれより少ない鉄合金である「鋼(はがね、Steel)」とは明確に区別されます。鋳鉄には炭素の他に、ケイ素が通常1~3%程度、さらにマンガン、リン、硫黄などが不純物または合金元素として含まれます。
その名の通り、鋳鉄の最大の利点は「鋳造」に適していることです。鋼に比べて融点が低く(約1150℃~1250℃)、溶けた状態での流動性が良いため、複雑な形状の製品でも型に流し込むことで比較的容易に製造できます。この優れた「鋳造性」により、古くから様々な製品の製造に用いられてきました。
鋳鉄の基本的な性質と炭素の役割
鋳鉄の様々な性質は、その高い炭素含有量と、その炭素が鉄の中でどのような形で存在しているかによって大きく左右されます。鋳鉄中の炭素は、主に以下の二つの形態で存在します。
- 黒鉛: 炭素原子が単体で結晶化したものです。ケイ素は黒鉛の生成を促進する重要な元素です。黒鉛が存在すると、鋳鉄は以下のような性質を示しやすくなります。
- 比較的柔らかく、切削加工がしやすい。
- 摩擦係数が低く、摩耗しにくい)。
- 振動を吸収しやすい。
- 熱を伝えやすい。
- ただし、黒鉛の形状が材料内部で切り欠きのように作用し、強度や延性、靭性を低下させる原因にもなります。
- セメンタイト: 炭素が鉄と化合してできた、非常に硬い金属間化合物です。ケイ素含有量が少ない場合や、溶けた鋳鉄が急速に冷却された場合に生成しやすくなります。セメンタイトが多く存在すると、鋳鉄は以下のような性質を示します。
- 極めて硬く、耐摩耗性に非常に優れる。
- 非常に脆く、衝撃に弱い。
- 切削加工が極めて困難。
鋳鉄の主な種類と特徴
鋳鉄は、主に内部に存在する黒鉛の形状や、基地の組織によって分類され、それぞれ異なる特性と用途を持っています。
- ねずみ鋳鉄: 最も一般的で広く使われている鋳鉄です。炭素の大部分が片状の黒鉛として析出しています。破面がねずみ色に見えることからこの名が付きました。優れた鋳造性、被削性、振動減衰能、耐摩耗性、熱伝導性を持ち、比較的安価です。しかし、片状黒鉛が応力集中を引き起こすため、引張強さや延性・靭性は低く、脆い材料です。機械のベッド(基盤)やフレーム、ケーシング、マンホールの蓋、水道のバルブ、エンジン部品の一部、調理器具に用いられます。JIS記号ではFCで表されます(例: FC200)。
- ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄、FCD材、Ductile/Nodular Cast Iron): 溶けたねずみ鋳鉄にマグネシウム(Mg)やセリウム(Ce)などを少量添加する「球状化処理」を行うことで、黒鉛が球状になって析出した鋳鉄です。黒鉛が球状であるため、ねずみ鋳鉄のような応力集中が起こりにくく、鋼に匹敵する高い引張強さ、延性、靭性を持っています。ねずみ鋳鉄の持つ良好な鋳造性、被削性、耐摩耗性なども兼ね備えています。水道管、自動車部品、産業機械の強度部品、マンホールの蓋など、高い強度と信頼性が要求される用途に不可欠な材料です。JIS記号ではFCDで表されます(例: FCD450)。
- 白鋳鉄(はくちゅうてつ、White Cast Iron): 炭素が黒鉛としてほとんど析出せず、硬くて脆いセメンタイト(Fe₃C)として晶出した鋳鉄です。ケイ素含有量を低く抑えたり、急速冷却したりすることで製造されます。破面が白く金属光沢を呈することからこの名があります。極めて硬く、耐摩耗性に非常に優れていますが、靭性が極めて低く脆いため、構造用材料には向きません。また、硬すぎて機械加工は困難です。粉砕機用のボールやライナー、圧延ロール、ポンプのインペラーなど、高い耐摩耗性が要求される部品に限定的に使用されます。また、後述する可鍛鋳鉄の素材としても重要です。
- 可鍛鋳鉄(かたんちゅうてつ、Malleable Cast Iron): 白鋳鉄を長時間かけて高温で熱処理し、脆いセメンタイトを分解させて、不定形な塊状の黒鉛を基地中に析出させた鋳鉄です。これにより、ねずみ鋳鉄よりも優れた延性、靭性が得られ、衝撃にもある程度耐えられるようになります。「可鍛」の名は、ある程度の塑性加工が可能であることに由来しますが、実際にはほとんど鋳放しのまま使われます。かつては自動車部品や管継手、電気部品などに広く使われましたが、製造に手間がかかることや、ダクタイル鋳鉄の性能向上により、その需要は減少傾向にあります。
- CV黒鉛鋳鉄(Compacted Graphite Iron, CGI): 黒鉛の形状が、ねずみ鋳鉄の片状とダクタイル鋳鉄の球状の中間の形態、すなわち短く厚みがあり、先端が丸まったいも虫状になった鋳鉄です。ねずみ鋳鉄よりも強度や剛性が高く、ダクタイル鋳鉄よりも熱伝導性や振動減衰能、鋳造時の湯流れ性が良いという、両者の中間的な優れた特性バランスを持ちます。高い強度と良好な熱特性が要求される自動車用高性能エンジンのシリンダーブロックやシリンダーヘッド、排気マニホールドなどに採用が拡大しています。
- 合金鋳鉄(ごうきんちゅうてつ、Alloy Cast Iron): 上記の鋳鉄に、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、銅(Cu)、バナジウム(V)などの合金元素を意図的に添加し、耐熱性、耐食性、耐摩耗性、強度、硬度などの特定の性質を向上させた鋳鉄の総称です。例えば、高クロム鋳鉄は耐摩耗性や耐熱性に優れ、ニッケルを多く含むオーステナイト鋳鉄は耐食性や耐熱性、非磁性に優れます。
鋳鉄の製造(鋳造プロセス)
鋳鉄部品は主に鋳造によって作られます。原材料となる銑鉄、鉄スクラップ、回収された鋳鉄、加炭材、ケイ素やマンガンなどの合金鉄を、キュポラや誘導炉などの溶解炉で溶解します。溶けた鉄の化学成分を分析し、目標の成分になるように調整した後、砂や金属で作られた鋳型に流し込みます。溶湯が冷えて凝固した後、鋳型から取り出し、砂や不要な部分を除去し、必要に応じて熱処理や機械加工、塗装などを施して製品となります。
鋳鉄の利点と欠点
- 利点:
- 複雑な形状のものを容易に作れる(優れた鋳造性)。
- 切削加工がしやすい。
- 振動を吸収する能力が高い。
- 摩耗しにくい。
- 鋼に比べて一般的に製造コストが安い。
- 種類が多く、用途に応じて様々な特性を選べる。
- 欠点:
- 一般的に鋼に比べて引張強さや延性・靭性が低く、脆い。
- 衝撃に対する抵抗力が低い。
- 溶接が難しい場合が多い。
まとめ
鋳鉄は、高い炭素含有量に由来する優れた鋳造性を基本としつつ、内部の黒鉛形態や基地組織を制御することで、多種多様な特性を引き出すことができる、非常に奥深く、かつ実用的な金属材料です。ねずみ鋳鉄の優れた減衰能や被削性、ダクタイル鋳鉄の高い強度と靭性、白鋳鉄の卓越した耐摩耗性など、それぞれの特徴を活かして、自動車産業、工作機械、水道・ガスなどのインフラ、さらには私たちの身近な調理器具に至るまで、現代社会のあらゆる場面で幅広く利用されており、ものづくりを支える基礎素材として不可欠な存在であり続けています。


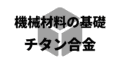
コメント