
機械材料の基礎:高速度工具鋼(ハイス)
高速度工具鋼は、金属を削るための切削工具の材料として、現代の製造業において極めて重要な位置を占める鉄鋼材料です。一般にハイスピードスチール、あるいは単にハイスという略称で広く親しまれています。日本産業規格 JIS においては SKH という記号で分類され、ドリル、エンドミル、タップ、ホブカッター、バイトなど、多種多様な切削工具の素材として使用されています。
この材料が登場する以前、金属加工には炭素工具鋼が用いられていました。しかし、炭素工具鋼は摩擦熱に弱く、切削速度を上げると刃先が焼き戻されて軟化し、すぐに切れなくなってしまうという欠点がありました。19世紀末から20世紀初頭にかけて開発された高速度工具鋼は、その名の通り、従来よりもはるかに高速での切削を可能にしました。これは、生産効率を劇的に向上させ、産業革命以降の機械文明の発展を根底から支えた歴史的な発明の一つと言えます。
赤熱硬性と二次硬化
高速度工具鋼の最大の特徴は、高温環境下でも硬さを失わないという性質にあります。
温度と硬さの関係
一般的な炭素鋼は、摂氏200度から300度程度に加熱されると、マルテンサイト組織が分解し、急速に硬度が低下してしまいます。しかし、高速度工具鋼は、摂氏600度付近まで加熱されても、常温と同等の高い硬度を維持し続けます。切削加工において、刃先は被削材との摩擦や塑性変形熱によって容易に摂氏500度以上に達します。金属が暗い赤色に発光するほどの高温になっても軟化せずに切削能力を維持できるこの性質こそが、ハイスと呼ばれる所以です。
二次硬化のメカニズム
この赤熱硬性を支えているのが、焼戻し処理によって硬さが再上昇する二次硬化という現象です。 高速度工具鋼は、焼入れ直後の状態では、炭素と合金元素が過剰に固溶したマルテンサイト組織と、未溶解の炭化物、そして残留オーステナイトから構成されています。これを摂氏550度から600度程度の温度で焼戻しを行うと、残留オーステナイトがマルテンサイトに変態すると同時に、タングステンやモリブデン、バナジウムといった合金元素が炭素と結合し、極めて微細な炭化物を析出させます。 この微細析出炭化物が、転位の移動を強力に妨げる効果を発揮し、母材を強化します。一般的な鋼が焼戻しによって軟化するのに対し、高速度工具鋼は合金炭化物の析出硬化によって逆に硬くなるのです。この特殊な挙動により、切削熱がかかる環境下でも高い耐摩耗性を発揮します。
合金元素の役割と化学組成
高速度工具鋼は、鉄をベースにしつつ、多種類の合金元素を多量に添加した高合金鋼です。それぞれの元素が特定の機能を担い、複雑な相互作用によって性能を決定づけています。
タングステン W とモリブデン Mo
これらは高速度工具鋼の主役となる元素です。炭素と結合して、M6C型と呼ばれる複合炭化物を形成します。この炭化物は熱に対して非常に安定であり、高温下での硬さを維持する赤熱硬性の主因となります。 かつてはタングステンを18パーセント含む鋼種が主流でしたが、資源的な制約や比重の問題から、現在ではタングステンの代わりにモリブデンを添加したモリブデン系ハイスが主流となっています。原子量換算で、モリブデンはタングステンの約半分の重量で同等の効果を発揮するため、材料の軽量化やコストダウンにも寄与します。
クロム Cr
ほぼ全ての高速度工具鋼に約4パーセント程度添加されています。クロムの主たる役割は、焼入れ性の向上です。空冷に近い緩やかな冷却速度であっても、材料の深部まで確実に焼きが入るようにします。また、耐酸化性を向上させ、熱処理時の表面劣化を防ぐ効果もあります。
バナジウム V
バナジウムは炭素と極めて強く結合し、MC型と呼ばれる非常に硬い炭化物を形成します。このMC炭化物は、ビッカース硬度で3000近くに達し、あらゆる炭化物の中でトップクラスの硬さを持ちます。 この硬い粒子が基地組織中に分散することで、対磨耗性が飛躍的に向上します。バナジウムの添加量が多いほど耐摩耗性は高くなりますが、同時に砥石による研削加工が困難になるという側面もあります。
コバルト Co
コバルトは炭化物を形成しない元素ですが、鉄の基地、マトリックスに固溶することで、その耐熱性を高める効果があります。具体的には、マトリックス中の合金元素の拡散を遅らせ、高温下での炭化物の凝集や粗大化を防ぎます。 これにより、さらに高温領域での硬さ維持が可能となるため、ステンレス鋼や耐熱合金などの難削材加工用として、コバルトを5パーセントから10パーセント添加したコバルトハイスが広く使用されています。
製造プロセスと粉末冶金法
高速度工具鋼の性能は、その製造プロセスによっても大きく左右されます。特に、炭化物の分布状態が工具の寿命や靭性を決定します。
溶解法とその限界
伝統的な製造法は、電気炉で原料を溶解し、インゴットに鋳造した後、圧延や鍛造を行って棒材や板材にする溶解法です。 しかし、高速度工具鋼のように合金元素を多量に含む材料では、凝固する際に成分の偏り、すなわち偏析が発生しやすくなります。凝固速度の遅い大型のインゴットでは、炭化物が巨大な網目状の組織、共晶炭化物ネットワークを形成してしまいます。 この巨大炭化物は、圧延工程で砕かれて縞状に並びますが、完全に均一化することは困難です。粗大な炭化物の塊や偏析は、工具の靭性を低下させ、熱処理時の歪みや、使用中の欠け、チッピングの原因となります。
粉末冶金法の革新
この偏析問題を解決したのが、粉末ハイスあるいは粉末冶金法と呼ばれる技術です。 溶解した溶湯を、高圧ガスで吹き飛ばして霧状にし、瞬時に凝固させて微細な粉末にします。アトマイズ法と呼ばれるこの工程では、粉末の一粒一粒が急速凝固するため、偏析が起きる暇がなく、極めて微細で均一な炭化物が分散した組織が得られます。
この粉末をカプセルに封入し、高温高圧下で焼き固める熱間等方圧加圧法、HIP処理を行うことで、完全に緻密な鋼材とします。粉末ハイスは、溶解ハイスに比べて靭性が高く、研削性も良好で、熱処理変形も少ないという理想的な特性を持ちます。これにより、従来は製造不可能だった高バナジウム含有の高合金ハイスの実用化が可能となりました。
熱処理技術の勘所
高速度工具鋼は、適切な熱処理を施して初めて工具としての性能を発揮します。
焼入れ
焼入れ温度は、融点に近い摂氏1180度から1240度という高い温度域に設定されます。これは、炭化物形成元素であるタングステンやバナジウム、および炭素を、可能な限りマトリックス中に固溶させるためです。 固溶量が多いほど、後の焼戻しでの二次硬化量が大きくなります。しかし、温度が高すぎたり保持時間が長すぎたりすると、結晶粒が粗大化して靭性が低下したり、粒界が溶融したりするリスクがあります。したがって、数度の単位での精密な温度制御が必要です。
焼戻し
焼入れされた材料は、極めて不安定で脆い状態にあります。また、焼入れ時にマルテンサイトに変態しきれなかった残留オーステナイトが多量に残っています。 焼戻しは、摂氏550度付近で複数回、通常は2回から3回繰り返して行われます。 1回目の焼戻しで、残留オーステナイトの一部がマルテンサイト化し、同時に微細炭化物の析出が始まります。冷却後、新たに生成したマルテンサイトをさらに焼戻すために2回目、3回目の処理を行います。この繰り返し処理によって、組織全体が安定化し、最高の硬さと必要な靭性を兼ね備えた状態に仕上がります。
サブゼロ処理
寸法安定性が特に求められるゲージや精密工具の場合、焼入れ後にマイナス80度以下、時には液体窒素温度まで冷却するサブゼロ処理を行うことがあります。これにより、残留オーステナイトを強制的にマルテンサイト変態させ、経年変化による寸法狂いを防ぎます。
材料規格と分類
JIS規格における高速度工具鋼 SKH は、大きくタングステン系とモリブデン系の二つに分類されます。
タングステン系 T系
SKH2、SKH3などが該当します。タングステンを主成分とする伝統的な鋼種です。耐摩耗性に優れますが、靭性はやや劣ります。タングステンが高価で比重が重いため、現在では特殊な用途を除き、使用量は減少傾向にあります。
モリブデン系 M系
SKH51、SKH55などが該当します。タングステンの一部または全部をモリブデンとバナジウムで置き換えた鋼種です。 中でもSKH51は、靭性と耐摩耗性のバランスが良く、熱処理も比較的容易であるため、ドリルやエンドミルなどの汎用工具として最も広く普及しています。コバルトを含有させたSKH55などは、耐熱性が高く、ステンレス鋼などの難削材加工に用いられます。
超硬合金との比較と共存
現代の切削工具市場において、高速度工具鋼の強力なライバルであり、多くの領域で主役の座を奪ったのが超硬合金です。しかし、高速度工具鋼が不要になったわけではありません。両者は特性に応じた明確な住み分けがなされています。
硬さと靭性のトレードオフ
超硬合金は、タングステンカーバイドなどの硬質粒子をコバルトで焼結した複合材料であり、高速度工具鋼よりもはるかに硬く、高速切削が可能です。 しかし、超硬合金は靭性が低く、衝撃に弱いという欠点があります。断続的な衝撃がかかる加工や、機械の剛性が低い場合、あるいは工具自体が細長くたわみやすい場合には、欠けや折損が発生しやすくなります。 対して高速度工具鋼は、金属材料としての粘り強さ、すなわち靭性に優れています。振動や衝撃を吸収し、欠けることなく耐える能力が高いため、不安定な切削条件下では依然として信頼性の高い選択肢となります。
成形性とコスト
高速度工具鋼は、焼入れ前であれば通常の鋼と同様に切削加工が可能であり、複雑な形状の工具を容易に製造できます。ギア加工用のホブカッターや、複雑な段付きドリル、ブローチなどは、高速度工具鋼の独壇場です。 また、材料コストにおいても超硬合金より安価であるため、小径ドリルやタップのような消耗品的性格の強い工具では、経済的な優位性があります。
表面処理による延命化
高速度工具鋼の性能をさらに引き上げる技術として、物理蒸着法 PVD による硬質皮膜コーティングが標準化しています。
TiNコーティング
最も一般的なのが窒化チタン TiN コーティングです。金色を呈するこの皮膜は、ビッカース硬度2000以上を持ち、摩擦係数も低いため、工具の摩耗を防ぎ、切り屑の溶着を抑制します。
TiAlNコーティング
窒化チタンアルミニウム TiAlN は、耐熱性をさらに高めたコーティングです。高温になると表面にアルミナの保護膜を形成するため、高速切削やドライ加工において、ハイス母材を熱から守る断熱材のような役割を果たします。 これらのコーティング技術と粉末ハイスを組み合わせることで、高速度工具鋼は超硬合金の領域に迫る性能を発揮する場合もあります。
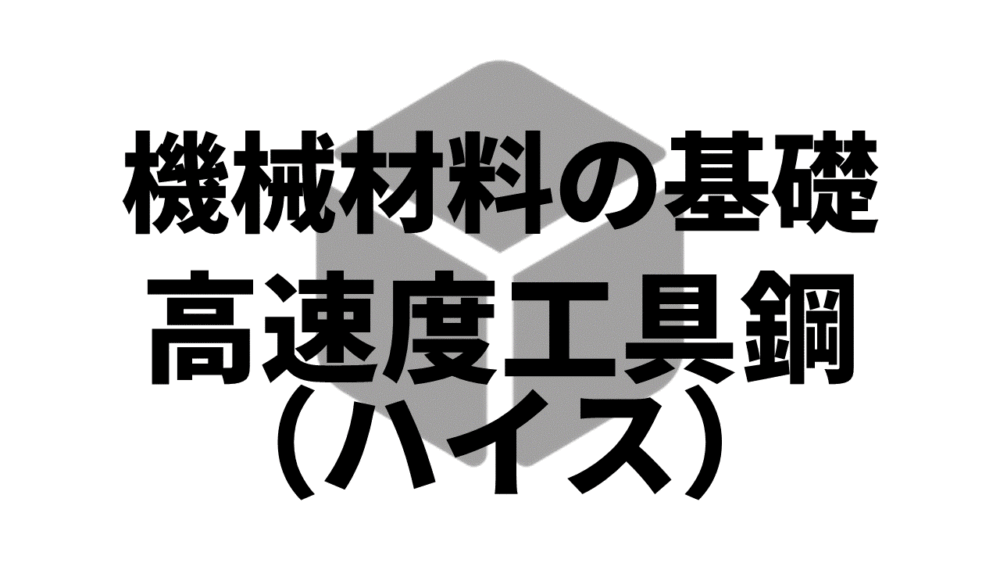


コメント