
機械要素の基礎:軸
軸とは
軸は、機械を構成する最も基本的な要素の一つであり、通常は断面が円形の棒状の部品です。その主な役割は、動力を伝達すること、運動を伝達すること、あるいは歯車、プーリー、スプロケット、はずみ車(フライホイール)、クランクなどの回転する部品を、それらが円滑に回転できるように支持することです。ほとんど全ての回転機械には、その機能を実現するための中心的な部品として軸が組み込まれており、機械全体の性能、精度、耐久性に直接的な影響を与える重要な要素です。
軸の機能と種類
軸は、その主たる機能や受ける荷重の種類によって、以下のように分類されることがあります。
- 伝動軸: 主にトルクを伝達し、動力を伝えることを目的とした軸です。トルクによる「ねじり応力」と、取り付けられた部品の重量や伝達される力による「曲げ応力」を同時に受けることが一般的です。自動車のドライブシャフトやプロペラシャフト、減速機や変速機の内部で歯車などを支えながら動力を伝える軸などがこれに該当します。
- 車軸: 主に車輪や回転ドラムなどを支え、それらにかかる荷重を支持することを目的とした軸です。多くの場合、自身は回転せず、回転する部品をベアリングを介して支えるか、部品と共に回転する場合でも大きなトルクは伝達しません。ただし、自動車の駆動輪のように回転してトルクを伝達する車軸もあり、伝動軸との明確な区別が難しい場合もあります。
- 主軸: 工作機械において、工作物または切削工具を取り付けて、高精度に回転させるための中心となる軸です。高い回転精度(振れ精度)、高い剛性、耐振動性、そして多くの場合、高速回転能力が要求されます。
- クランク軸: 主にレシプロエンジン(自動車エンジンなど)において、ピストンの往復直線運動を回転運動に変換するために用いられる、クランク機構を持つ複雑な形状の軸です。逆に、ポンプや圧縮機などでは、回転運動を往復運動に変換するために使われることもあります。
- カム軸: 断面が円形ではなく、特定の輪郭形状を持つカム(偏心輪)が一体または別体で取り付けられた軸です。カム軸が回転することで、カムが接触している別の部品(従節、フォロワ。例:エンジンのバルブ)を往復運動または揺動運動させます。主にレシプロエンジンの吸排気バルブを開閉するタイミングを制御するために用いられます。
- フレキシブルシャフト: ワイヤーをコイル状に巻くなどして作られ、曲げることができるにも関わらず回転(トルク)を伝達できる特殊な軸です。動力を入り組んだ場所に伝えたい場合や、駆動側と被動側の相対位置が変動する場合などに利用されます。
軸が受ける荷重と応力
軸は、その機能を発揮する過程で様々な種類の荷重を受け、その内部には応力が発生します。
- ねじり): トルク伝達に伴って発生する、軸をねじるような荷重。せん断応力を生じさせます。
- 曲げ: 取り付けられた歯車、プーリー、ベルトなどからの力、あるいは軸自身の重量などによって、軸を曲げようとする荷重。引張応力と圧縮応力を生じさせます。
- 軸方向荷重: 軸の長手方向に作用する引張または圧縮の荷重(スラスト荷重)。例えば、はすば歯車やプロペラなどから発生します。引張応力または圧縮応力を生じさせます。
多くの場合、軸はこれらの荷重が複合的に作用します。特に回転する軸では、曲げ応力が繰り返し変動するため、材料の「疲労(ひろう)」が破壊の主な原因となることが多く、設計上最も注意が必要です。
軸の設計における重要事項
信頼性が高く、効率的な軸を設計するためには、以下の点を十分に考慮する必要があります。
- 強度: 軸が使用中に受ける最大の応力に対して、破壊したり、永久変形したりしないこと。材料の強度(引張強さ、降伏点、疲労限度など)と、後述する応力集中を考慮して、十分な安全率を見込んだ設計が必要です。
- 剛性: 荷重を受けた際の軸の変形が、機能上許容できる範囲内に収まること。例えば、歯車を支える軸のたわみが大きいと、歯車の噛み合いが悪くなり、騒音や摩耗、伝達効率の低下を引き起こします。軸受部の傾きも軸受の寿命に影響します。多くの場合、強度よりもこの剛性の条件(許容たわみ量、許容ねじれ角)によって軸の太さ(直径)が決まります。
- 振動と危険速度): 回転する軸には、その寸法、質量、支持方法によって決まる固有の振動数があります。軸の回転速度がこの固有振動数(またはその整数倍)と一致すると、共振現象が発生し、振幅が急激に増大して危険な状態(危険速度)となります。軸の設計においては、通常の運転速度が危険速度から十分に離れるように、軸の寸法や支持方法を決定する必要があります。
- 応力集中): 軸には、キー溝(キーを取り付けるための溝)、段部(軸径が変化する部分)、油穴、ねじ部など、形状が不連続に変化する部分が多く存在します。これらの部分では応力が局部的に集中し、公称応力(単純計算上の応力)よりもはるかに高い応力が発生します。特に疲労破壊は、このような応力集中部から発生することが多いため、設計においては応力集中をできるだけ避けるか、影響を緩和することが重要です。
軸の材料
軸に使用される材料は、要求される強度、剛性、耐疲労性、耐摩耗性、耐食性、加工性、経済性などを総合的に考慮して選定されます。
- 炭素鋼: S35C、S45C、S50Cなど。最も一般的に使用される材料です。必要に応じて熱処理(焼ならし、焼入れ焼戻し)が施されます。
- 合金鋼: ニッケルクロム鋼(SNC材)、クロムモリブデン鋼(SCM材)、ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM材)など。炭素鋼よりも高い強度、靭性、耐疲労性が要求される場合に使用され、多くの場合、調質(焼入れ焼戻し)などの熱処理によって性能が最大限に引き出されます。
- ステンレス鋼: 耐食性が特に要求される場合に使用されます。SUS304、SUS316(オーステナイト系)、SUS420J2などがあります。
- その他、用途によっては鋳鉄やアルミニウム合金、チタン合金などが用いられることもあります。
軸に付随する形状や要素
軸には、他の機械要素を取り付けたり、軸自身を支持したりするために、様々な形状が付加されています。
- 軸受部: 軸を回転自在に支持するための軸受がはめ合わされる部分です。正確な寸法公差と滑らかな表面仕上げ(粗さ)が要求されます。
- キー溝、スプライン、セレーション: 歯車、プーリー、カップリングなどの回転部品と軸の間でトルク(回転力)を確実に伝達するために設けられる形状です。キーとキー溝、多歯のかみ合いであるスプラインやセレーションなどが用いられます。これらは応力集中源となるため、設計上の配慮が必要です。
- 段部: 軸の直径が変化する部分です。部品を軸方向に正確に位置決めしたり、軸受や歯車などの側面を受けるための「つば」として機能したりします。
- ねじ部: ナットを用いて部品を軸に固定したり、部品の位置を調整したりするために、おねじが切られます。
- 表面処理: 軸受部やオイルシールが接触する部分の耐摩耗性を向上させる目的で、高周波焼入れ、浸炭焼入れ、窒化処理などの表面硬化処理が施されることがあります。また、耐食性向上のために硬質クロムめっきなどが施される場合もあります。
軸の製造
軸は、一般的に丸棒鋼材を主な素材として、旋盤による切削加工(旋削)や、研削盤による研削加工によって製作されます。クランク軸のような複雑な形状や、特に高い強度・靭性が要求される場合には、鍛造によって素材の形状を作り、内部組織を緻密化することもあります。多くの場合、所定の強度や硬さを得るために熱処理工程が含まれます。高速で回転する軸では、回転時の振動を防ぐために、精密な質量分布の調整が行われます。
まとめ
軸は、回転運動を伴うあらゆる機械において、動力や運動を伝達し、回転部品を支持するという根幹的な機能を担う、極めて重要な機械要素です。その設計においては、単に力を伝えるだけでなく、強度、剛性、振動、応力集中、材料の選定、加工精度など、多岐にわたる要素を総合的に考慮する必要があります。適切に設計・製作された軸は、機械全体の性能、効率、そして何よりも安全な運転を保証するための基盤となります。
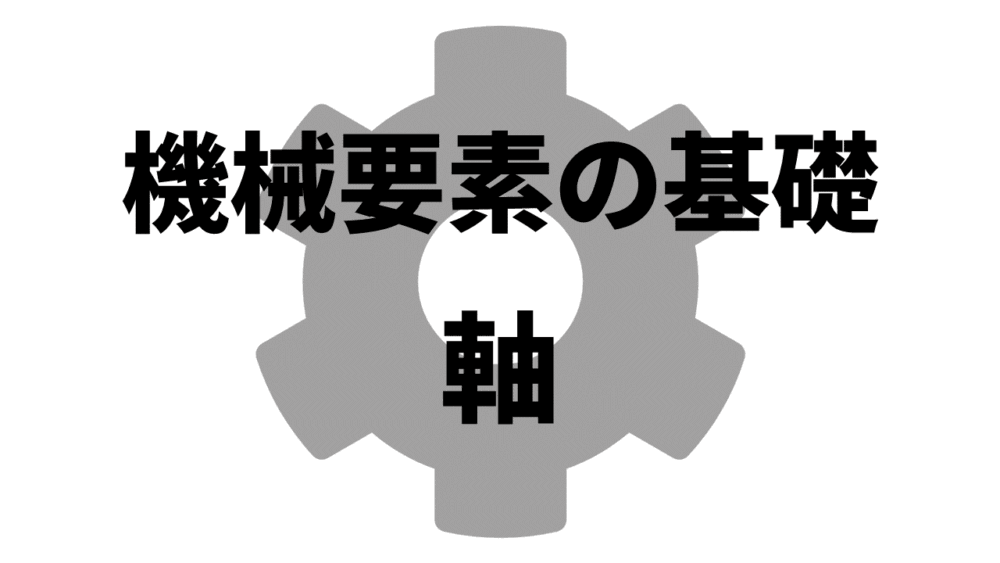
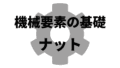
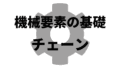
コメント