熱電対は、二種類の異なる金属導体を接合し、その両端に生じる温度差によって発生する起電力を利用して温度を測定するセンサです。
現代の産業界において、温度計測は最も基本的かつ重要な測定値です。溶鉱炉で溶けた鉄の温度から、半導体製造装置内の微細な温度分布、あるいは家庭用ガステーブルの安全装置に至るまで、熱電対はそのシンプルさと堅牢さ、そして広い測定範囲によって、温度センサの代名詞として不動の地位を築いています。測温抵抗体やサーミスタといった他のセンサと比較しても、その応答速度の速さと汎用性は群を抜いています。
ゼーベック効果と熱起電力
熱電対の動作原理は、ドイツの物理学者トーマス・ゼーベックによって発見されたゼーベック効果に基づいています。
電子の拡散と電位差
二つの異なる金属、例えば銅とコンスタンタンという合金を用意し、それぞれの両端を繋ぎ合わせて閉回路を作ります。一方の接合点を加熱し、もう一方の接合点を冷却して温度差を与えると、回路中に電流が流れます。このとき発生する電圧を熱起電力と呼びます。
金属内部には自由に動き回れる自由電子が存在します。金属棒の一端を加熱すると、その部分の自由電子は熱エネルギーを得て運動エネルギーが増大し、激しく振動しながら低温側へと拡散していきます。これは気体分子が濃度の高い方から低い方へ拡散するのと似た現象です。
高温側から低温側へ電子が移動すると、低温側は電子過剰となってマイナスに帯電し、高温側は電子不足となってプラスに帯電します。この電荷の偏りによって金属内部に電界が生じ、これ以上の電子の移動を妨げる力と、熱拡散しようとする力が釣り合った状態で電位差が安定します。
金属による仕事関数の違い
重要な点は、この電子の拡散度合い、すなわち発生する電位差の大きさが金属の種類によって異なるということです。 単一の金属線で両端に温度差をつけても、その金属内で電位差は生じますが、回路として閉じてしまうと同じ金属の戻り線で同じ大きさの逆起電力が発生して打ち消し合うため、外部からは電圧として観測できません。
しかし、異なる二種類の金属を接合した場合、それぞれの金属が持つ仕事関数や電子密度の違いにより、温度勾配に対する起電力の発生率が異なります。この二つの金属の起電力の差分を取り出すことで、初めて温度差に応じた電圧信号として検出することが可能になります。これが熱電対の正体です。
熱電対の基本法則
熱電対を用いて正しく温度を測るためには、いくつかの物理法則を理解しておく必要があります。
均質回路の法則
均質な金属線で構成された熱電対回路において、その起電力は両接点の温度だけで決まり、途中の温度分布には影響されないという法則です。 たとえ熱電対の素線の一部が局所的にバーナーで炙られていても、あるいは液体窒素に浸かっていても、素線が均質である限り、測定される起電力は温接点と冷接点の温度差のみに依存します。 逆に言えば、素線が経年劣化や腐食によって不均質になっている場合、途中の温度勾配が「寄生熱電対」として機能し、誤差を生む原因となります。
中間金属の法則
熱電対の回路中に第三の金属を挿入しても、その両端の温度が等しければ、回路全体の熱起電力には影響を与えないという法則です。 この法則のおかげで、私たちは熱電対の先端を溶接したり、端子台に銅のネジで固定したり、半田付けを行ったりすることができます。接続点さえ等温に保たれていれば、異種金属が介在しても測定値は狂わないのです。これは計測システムの構築において極めて重要な特性です。
中間温度の法則
ある温度T1とT2の間の熱起電力と、T2とT3の間の熱起電力を足し合わせると、T1とT3の間の熱起電力に等しくなるという法則です。 これにより、基準となる温度、通常は摂氏0度からの起電力特性テーブルさえ用意しておけば、任意の基準点温度における測定値を計算によって求めることが可能になります。
基準接点補償 冷接点補償
熱電対が測定するのは、あくまで二つの接点の温度差であって、測定対象の絶対温度ではありません。
氷点槽から電子回路へ
測定したい側の接点を測温接点あるいは温接点と呼び、計器に接続する側の接点を基準接点あるいは冷接点と呼びます。 計器が読み取る電圧は、温接点温度と冷接点温度の差に相当するものです。したがって、温接点の正しい温度を知るためには、冷接点の温度を一定に保つか、あるいは冷接点の温度を知る必要があります。 かつて実験室レベルでは、冷接点を氷と水が共存する魔法瓶、すなわち摂氏0度の氷点槽に入れて基準を固定していました。しかし、産業現場で常に氷を用意することは不可能です。
現代の補償技術
現代の温度変換器や記録計では、基準接点補償という機能が標準装備されています。 これは、端子台付近にサーミスタや測温抵抗体などの別の温度センサを埋め込み、端子自体の温度、すなわち冷接点温度をリアルタイムで測定します。そして、その室温に相当する熱起電力を計算上で加算することで、あたかも冷接点が0度にあるかのような電圧値に補正し、正しい温度を表示します。 したがって、熱電対の端子台に直射日光が当たったり、エアコンの風が直撃したりして端子温度が不安定になると、この補正が追いつかず、測定値がふらつく原因となります。
熱電対の種類と材料特性
JISやIECなどの規格では、材料の組み合わせによって記号が定められています。それぞれの特性を理解し、用途に応じて選定することが重要です。
K熱電対 クロメル・アルメル
現在、産業界で最も広く使われているのがK熱電対です。プラス側にニッケル・クロム合金のクロメル、マイナス側にニッケル・アルミニウム合金のアルメルを使用します。 摂氏マイナス200度からプラス1200度程度までという非常に広い測定範囲を持ち、酸化雰囲気中での耐食性に優れています。また、起電力の直線性が良く、取り扱いが容易です。 ただし、還元雰囲気(水素や一酸化炭素など)では劣化しやすく、また摂氏300度から500度付近で短距離秩序構造の変化による特性のヒステリシスが生じるため、超精密測定には向きません。
J熱電対 鉄・コンスタンタン
プラス側に鉄、マイナス側に銅・ニッケル合金のコンスタンタンを使用します。 比較的安価で、K熱電対よりも起電力が大きいため感度が良いのが特徴です。 還元雰囲気でも使用できるという強みがありますが、プラス側の鉄が錆びやすいため、湿度の高い環境や酸化雰囲気での高温使用には適しません。欧米の樹脂成形機などで伝統的に多く使われています。
T熱電対 銅・コンスタンタン
プラス側に銅、マイナス側にコンスタンタンを使用します。 低温での特性が非常に安定しており、摂氏マイナス200度以下の極低温測定や、常温付近での精密測定に適しています。銅線を使用しているため、電気抵抗が低く、延長距離が長い場合でもノイズの影響を受けにくい利点があります。実験室や医療分野で多用されます。
R熱電対およびS熱電対 白金ロジウム・白金
貴金属である白金を使用するため非常に高価ですが、化学的に極めて安定しており、高温酸化雰囲気中でも長期間精度を維持できます。 Rはプラス側に白金ロジウム13パーセント、Sは10パーセントを含有します。摂氏1400度から1600度といった高温域での標準温度計として、またセラミックス焼成炉などの制御用として不可欠です。
B熱電対
プラス側に白金ロジウム30パーセント、マイナス側に白金ロジウム6パーセントを使用します。 融点が高く、摂氏1700度までの連続使用に耐えます。また、低温域での起電力が極めて小さいため、常温付近では基準接点補償を省略しても誤差が少ないという特殊な性質を持っています。
N熱電対 ナイクロシル・ナイシル
K熱電対の弱点を克服するために開発された比較的新しい熱電対です。 K熱電対に比べてクロムやシリコンの濃度を調整することで、高温での耐酸化性と原子構造の安定性を高めています。K熱電対のような経時変化が少なく、高価な白金熱電対の代替として期待されていますが、普及率ではまだK熱電対に及びません。
シース熱電対の構造
素線をそのまま露出させて使うことは稀で、通常は保護管や絶縁材と共にパッケージ化されます。中でも主流なのがシース熱電対です。
酸化マグネシウム絶縁
ステンレスやインコネルといった金属の細いパイプの中に、熱電対素線を挿入し、隙間に粉末状の酸化マグネシウムを充填して、高圧で圧縮封入した構造です。 酸化マグネシウムは、高温でも高い電気絶縁性を保ちつつ、熱伝導率は比較的良いという優れたセラミックスです。 この構造により、素線が外気から完全に遮断されるため、ガスによる腐食や酸化を防ぎ、寿命が飛躍的に延びます。また、全体が一体化しているため、曲げ加工が容易で、機械的な振動や衝撃にも強いという特徴があります。
接点形状のバリエーション
シース熱電対の先端形状には三つのタイプがあります。 一つ目は接地型です。測温接点をシースの先端に溶接し、金属外皮と導通させたものです。熱がダイレクトに伝わるため応答速度が最も速いですが、電気的ノイズを拾いやすく、漏電している対象物の測定には使えません。 二つ目は非接地型です。測温接点をシースから浮かせて絶縁したものです。応答速度はやや劣りますが、電気的に絶縁されているためノイズに強く、最も一般的に使用されます。 三つ目は露出型です。シースの先端から素線を露出させたものです。気体の温度変化などを極めて高速に捉えたい場合に使われますが、機械的強度や耐食性は低くなります。
補償導線の役割
熱電対の端子箱から計器室まで、数メートルから数百メートルの距離がある場合、高価な熱電対素線をそのまま延長するのは経済的ではありません。特に白金熱電対の場合、コストが莫大になります。
代替材料による延長
そこで用いられるのが補償導線です。これは、常温から摂氏100度程度の範囲において、熱電対本体とほぼ同等の熱起電力特性を持つ、安価な導体材料を絶縁被覆したケーブルです。 例えば、K熱電対用の補償導線には、本体とは成分の異なる銅・ニッケル合金などが使われます。 補償導線を使うことで、実質的に冷接点を計器室の入力端子まで延長したのと同じ効果が得られます。 注意すべきは、補償導線にはプラスマイナスの極性があり、誤って逆に接続すると、その温度差分だけ大きな誤差が生じることです。また、補償導線自体の耐熱温度はそれほど高くないため、炉壁などの高温部に触れないよう敷設する必要があります。
測定誤差と劣化要因
熱電対は堅牢ですが、永久不変ではありません。使用環境に応じた劣化メカニズムが存在します。
グリーンロット 緑色腐食
K熱電対特有の現象として、グリーンロットと呼ばれる腐食があります。 酸素濃度が低く、かつ還元性ガスが存在するような中途半端な環境下で摂氏800度から1000度で使用すると、プラス極のクロメル合金中のクロムだけが選択的に酸化されます。 通常、金属表面には緻密な酸化皮膜ができて内部を守りますが、酸素が不足すると皮膜が形成されず、内部へ酸化が侵攻します。この際、表面が緑色に変色するためこの名があります。 クロムが消費されると合金の組成が変わり、熱起電力が低下して、実際よりも低い温度を表示するようになります。これは断線せずに誤差だけが大きくなるため、発見が遅れやすく厄介なトラブルです。
シャントエラー
高温環境下では、絶縁材である酸化マグネシウムやセラミックスの電気抵抗が指数関数的に低下します。 すると、本来の測温接点よりも手前の部分で、絶縁不良により電流がリークし、短絡回路が形成されます。これをシャントエラーと呼びます。 あたかもその短絡場所に新しい接点ができたかのように振る舞うため、炉内の温度分布によっては、先端温度ではなく途中の低い温度を測定してしまい、制御系が「温度が低い」と判断してヒーター出力を上げ続け、オーバーヒート事故につながる恐れがあります。
熱伝導誤差
熱電対を保護管に入れて測定する場合、保護管自体を通して熱が外部へ逃げていきます。 特に被測定物の熱容量が小さい場合や、気体温度を測る場合、保護管の根元が冷えていると、先端から根元へ熱が奪われ、先端温度が周囲温度よりも低くなります。 これを防ぐためには、保護管の外径の15倍から20倍程度の長さを挿入し、熱伝導の影響を無視できる深さまで没入させる必要があります。
未来への展望と役割
デジタルセンサ全盛の現代においても、自ら発電し、外部電源を必要としない熱電対のアナログな原理は、信頼性の根幹として揺るぎないものです。
極限環境への挑戦
原子力発電所の炉心溶融温度監視や、航空宇宙エンジンのタービン温度監視など、半導体センサでは即座に破壊されるような過酷環境において、タングステン・レニウム合金などの特殊熱電対が開発され、人類の活動領域を支えています。
薄膜熱電対
また、MEMS技術の進展により、シリコンウェハー上にミクロン単位の薄膜熱電対を形成し、マイクロプロセッサの局所的な発熱を監視したり、化学反応セルの微小な熱収支を測定したりする技術も実用化されています。

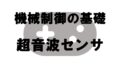

コメント