金属は叩けば硬くなる。これは古来より鍛冶職人たちが経験的に知っていた事実であり、日本刀の鍛錬や銅器の打ち出し加工などに見られるように、人類が金属文明を築き上げる過程で最も基本的かつ頻繁に利用してきた性質の一つです。
歪硬化とも呼ばれるこの現象は、金属材料に塑性変形を与えると、変形の進行に伴って変形抵抗が増大し、硬さや強度が上昇する性質を指します。針金を同じ場所で何度も折り曲げていると、次第に硬くなって曲げにくくなり、最終的には破断してしまいますが、これこそが加工硬化の典型的な例です。
現代の製造業において、加工硬化は諸刃の剣です。プレス成形や冷間鍛造においては、製品の強度を高めるための重要な強化機構として積極的に利用されます。一方で、切削加工や多段階の絞り加工においては、工具寿命を縮めたり、材料の割れを引き起こしたりする厄介なトラブル要因となります。
変形の物理学と転位論
金属の硬化メカニズムを理解するためには、原子レベルでの変形の仕組みを知る必要があります。
弾性変形と塑性変形
金属原子は規則正しく並んで結晶格子を形成しています。これに力を加えると、原子間の結合距離が伸び縮みします。これが弾性変形であり、力を除けばバネのように元に戻ります。 しかし、ある限界すなわち弾性限度を超えると、原子の列同士がずれて位置を変えます。一度ずれてしまうと、力を除いても元の位置には戻りません。これが塑性変形です。 理論的には、原子の列全体が一斉にずれるには莫大な力が必要ですが、実際の金属は理論値よりもはるかに小さな力で変形します。この乖離を説明するのが転位と呼ばれる結晶欠陥です。
転位の増殖と絡み合い
転位とは、結晶格子の並びの中に存在する線状の乱れのことです。カーペットの一部にできたシワを想像してください。カーペット全体を一度に動かすのは大変ですが、シワを端から端まで移動させることで、少ない力でカーペット全体をずらすことができます。金属の塑性変形もこれと同様に、転位が結晶内を移動することによって進行します。 加工硬化の本質は、この転位の移動が困難になることにあります。 金属を変形させると、フランク・リード源などの発生源から新たな転位が次々と生み出され、転位密度が飛躍的に増大します。焼鈍された軟らかい金属では1平方センチメートルあたり百万本程度である転位密度が、激しく加工された金属では一千億本以上に達することもあります。 数が増えた転位同士はお互いに干渉し合い、衝突し、絡まり合います。これを転位の林と呼びます。混雑した交差点で車が動けなくなるように、転位が動きにくくなることで、さらなる変形にはより大きな力が必要になります。これが、加工硬化の物理的な正体です。
応力-歪み線図とn値
材料の加工硬化特性を定量的に評価するために、引張試験で得られる応力-歪み線図が用いられます。
降伏点と流動応力
引張試験片を引っ張っていくと、弾性変形領域を経て降伏点に達し、塑性変形が始まります。 ここからさらに引っ張り続けると、応力は低下せず、むしろ上昇していきます。この塑性変形領域における応力を流動応力と呼びます。流動応力が歪みの増加とともに上昇する勾配が急であるほど、加工硬化しやすい材料であると言えます。
結晶構造と材料による違い
全ての金属が同じように硬化するわけではありません。原子の並び方、すなわち結晶構造によって、転位の動きやすさや絡まりやすさが異なるため、加工硬化の程度も大きく異なります。
面心立方格子 FCC
オーステナイト系ステンレス鋼(SUS304など)、アルミニウム、銅などが属します。 これらは一般的に加工硬化しやすい材料群です。特にオーステナイト系ステンレス鋼は、加工硬化のチャンピオンとも呼ぶべき性質を持っています。これは、積層欠陥エネルギーが低いために転位が拡張しやすく、交差すべりと呼ばれる障害物を回避する動きが起こりにくいためです。逃げ場を失った転位は蓄積し、著しい硬化をもたらします。 一方で、アルミニウムは積層欠陥エネルギーが高く、転位が障害物を回避しやすいため、ステンレスに比べると加工硬化率は低くなります。
体心立方格子 BCC
鉄(フェライト鋼)、クロム、モリブデンなどが属します。 これらはFCCに比べてすべり面が多く、複雑な挙動を示しますが、一般的に中程度の加工硬化を示します。炭素鋼においては、固溶している炭素原子が転位の動きを固着するコットレル効果や、動的歪時効によっても硬化挙動が影響を受けます。
六方最密充填構造 HCP
チタン、マグネシウム、亜鉛などが属します。 すべり系が限定されているため、転位が動ける方向が限られます。そのため、変形させること自体が難しく、加工硬化というよりも、双晶変形などのメカニズムが支配的になる場合があります。
製造プロセスにおける利点
加工硬化は、単なる物理現象ではなく、ものづくりにおける強力なツールとして利用されています。
冷間鍛造による高強度化
ボルトやナット、ギアなどの量産部品製造において、冷間鍛造は中心的な技術です。 常温で材料を金型に押し込んで成形することで、製品の形状を作ると同時に、加工硬化によって強度を高めることができます。熱処理を行わなくても、中炭素鋼などで高い引張強度を得ることが可能であり、これを調質省略鋼あるいは非調質鋼として利用することで、エネルギーコストと製造時間を大幅に削減しています。
ばね用材料
ピアノ線や硬鋼線などのばね材料は、伸線加工(ダイスを通した引き抜き)によって極限まで加工硬化させることで、強靭な弾性を獲得しています。断面積が数分の一になるまで引き伸ばされた組織は、繊維状に配向し、転位密度が極限まで高まった状態にあり、極めて高い降伏点を持ちます。
表面改質技術
ショットピーニングやバニシング加工は、加工硬化を表面のみに適用する技術です。 多数の鋼球を高速で投射したり、ローラーで表面を押し潰したりすることで、表層に塑性変形を与え、硬化させます。同時に圧縮残留応力を付与することで、疲労強度や耐摩耗性を劇的に向上させます。自動車のギアや航空機のエンジン部品には不可欠な処理です。
加工における課題とトラブル
一方で、意図しない加工硬化は、製造現場において数々のトラブルを引き起こす原因となります。
切削加工における難削性
ステンレス鋼や耐熱合金を切削する際、刃物が通過した直後の加工面は、激しい塑性変形を受けて硬化しています。これを加工変質層と呼びます。 次に刃物が通過するとき、この硬化した層を削らなければならないため、切削抵抗が増大し、刃先が欠けたり、摩耗が加速したりします。特に、ドリルのように中心部の切削速度が遅い工具では、硬化した層をこすり続けることになり、工具寿命が著しく短くなります。 対策としては、硬化層よりも深く切り込む設定にする、切れ味の良い工具を使う、冷却を徹底するなどが挙げられます。
プレス成形における割れとスプリングバック
多段階の絞り加工を行う場合、1工程目で硬化した材料を2工程目でさらに変形させようとすると、延性が尽きて割れが発生します。これを置き割れや時期割れと呼ぶこともあります。 また、加工硬化によって流動応力が上昇すると、弾性回復量も大きくなるため、金型から外した瞬間に形状が戻ってしまうスプリングバックが顕著になります。高張力鋼板(ハイテン材)のプレス成形において、寸法精度を出しにくいのはこのためです。
回復と再結晶によるリセット
加工硬化によって限界まで硬くなり、これ以上変形できなくなった材料を、再び加工可能な状態に戻すのが焼鈍(アニーリング)処理です。
内部エネルギーの解放
加工硬化した金属は、内部に大量の転位と歪みを抱え込み、エネルギー的に不安定な状態にあります。これを適切な温度に加熱すると、原子が動き出し、安定な状態へ戻ろうとします。 まず、転位同士が合体して消滅したり、整列したりする回復過程が起きます。 さらに温度を上げると、歪みのない新しい結晶核が生成され、それが古い組織を食いつぶすように成長していきます。これが再結晶です。 再結晶が完了すると、転位密度は加工前のレベルまで低下し、材料は軟化して延性を取り戻します。冷間圧延で作られる薄板や銅線などは、この「加工して硬化したら、焼鈍して軟化させる」というサイクルを繰り返すことで、最終的な厚みや線径まで加工されます。
特殊な加工硬化現象
近年の材料科学の進歩により、従来の常識を超えた加工硬化特性を持つ材料が開発されています。
TRIP鋼とTWIP鋼
自動車の衝突安全性と軽量化を両立するために開発されたのが、変態誘起塑性(TRIP)鋼や、双晶誘起塑性(TWIP)鋼です。 TRIP鋼は、変形中に不安定な残留オーステナイトが硬いマルテンサイトへ変態することで、局所的な硬化を起こし、高い延性を維持しながら強度を上げます。 TWIP鋼は、変形中に結晶内に双晶(クリスタルの鏡像反転領域)が多数発生し、それが転位の障壁となることで、驚異的な加工硬化率と伸びを実現しています。
超微細粒組織
巨大ひずみ加工(SPD)などの特殊な手法を用いて、結晶粒径をナノメートルレベルまで微細化すると、加工硬化のメカニズムが変化し、従来の粗大粒材料とは異なる高強度と延性のバランスを示すことが分かってきています。

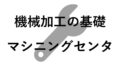
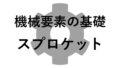
コメント