ポンプは、液体や気体といった流体に、羽根車やピストンの運動を通じて機械的なエネルギーを与え、それを圧力や速度のエネルギーに変換することで、流体を低い場所から高い場所へ、あるいは低い圧力の場所から高い圧力の場所へと輸送する機械です。その役割は、人体の心臓が血液を全身に送り出すのと同様に、あらゆる流体システムの根幹をなすものであり、私たちの生活や産業活動に不可欠な存在です。
ポンプと一言で言っても、その作動原理によって多種多様な形式が存在します。工学的には、そのエネルギーの与え方によって、大きく非容積式ポンプと容積式ポンプの二つのファミリーに大別されます。。
非容積式ポンプ(ターボ形ポンプ)
非容積式ポンプは、羽根車(インペラ)と呼ばれる部品を高速で回転させ、その運動エネルギーを流体に与えることで、流体を輸送するポンプです。連続的に流体を扱うため、脈動のない滑らかな流れが得られるのが特徴です。
遠心ポンプ
非容積式ポンプの中で最も代表的で、世界で最も広く使用されているのが遠心ポンプです。その構造は、中心から放射状に羽根が伸びた羽根車と、それを取り囲む渦巻きケーシングからなります。
- 作動原理:
- 液体は、羽根車の中心にある吸込口から吸い込まれます。
- モーターによって高速で回転する羽根車は、吸い込まれた液体に強力な遠心力を与え、外周方向へと勢いよく放り出します。これにより、液体は高い運動エネルギー(速度)を得ます。
- 羽根車から放り出された液体は、渦巻きケーシングに沿って流れます。このケーシングは、出口に向かうにつれて、その流路断面積が徐々に広がるように設計されています。
- 流路が広がることで、液体の流速は徐々に遅くなります。このとき、ベルヌーイの定理に従い、失われた運動エネルギーが圧力エネルギーへと変換され、液体の圧力が上昇します。
このように、遠心ポンプは、羽根車で与えた「速度」を、ケーシングで「圧力」に変換するという、二段階のプロセスで液体を送り出しています。
特性
遠心ポンプの吐出する流量は、配管の抵抗などによって生じる背圧(揚程)によって大きく変化します。吐出側のバルブを完全に閉じると、流量はゼロになりますが、圧力は最大値を示し、ポンプが破損することはありません。この柔軟な特性から、上水道や工業用水の供給、化学プラント、冷暖房の循環水など、極めて幅広い用途で利用されています。
容積式ポンプ
容積式ポンプは、ポンプ内部にある密閉された空間の容積を、周期的に変化させることで、液体を吸い込み、そして機械的に押し出すポンプです。一定の容積を確実に送り出すため、その吐出流量は、ポンプの回転速度にほぼ比例し、背圧の影響をほとんど受けないという、非容積式とは対照的な特性を持ちます。
往復ポンプ
ピストンやプランジャがシリンダ内を往復運動することで、液体を吸入・吐出します。注射器の原理と同様に、一度に送り出す量は少ないですが、極めて高い圧力を発生させることができるのが最大の特徴です。高圧洗浄機や油圧装置などに用いられます。
回転ポンプ
歯車や羽根、ねじといった回転体の運動を利用して、液体を移送します。
- 歯車ポンプ: 二つの歯車がかみ合いながら回転することで、歯とケーシングの間に液体を閉じ込め、吸込側から吐出側へと運びます。構造が単純で堅牢なため、油圧装置の動力源や、粘度の高い液体の移送に広く利用されています。
- ねじポンプ: 複数本のねじがかみ合いながら回転し、ねじの谷間に閉じ込められた液体を、軸方向に連続的に移送します。脈動が非常に少なく、静粛性に優れています。
容積式ポンプは、吐出側のバルブを閉じると、行き場を失った液体によって内部の圧力が無限に上昇し、ポンプや配管を破壊する危険があるため、必ずリリーフ弁などの安全装置を設置する必要があります。
ポンプの選定と重要特性
ポンプを選定する上で、最も重要なのがポンプの性能曲線を理解することです。
性能曲線と運転点
揚程とは、ポンプが液体をどれくらいの高さまで持ち上げられるかを示す、圧力の指標です。遠心ポンプの性能曲線は、横軸に流量、縦軸に揚程をとったグラフで表され、一般に「流量が増えるほど、揚程は低下する」という右下がりの曲線を描きます。
一方、実際に液体を流す配管システムにも、摩擦などによる抵抗が存在し、「流量が増えるほど、より大きな揚程が必要になる」という抵抗曲線が描かれます。
ポンプを選定するとは、このポンプの性能曲線と配管の抵抗曲線を重ね合わせ、その交点である運転点が、目的の流量と揚程を満足するかどうかを確認する作業です。
キャビテーション
ポンプの運転において、最も注意すべき、破壊的な現象がキャビテーションです。
- 発生原理: ポンプの吸込側で圧力が極端に低下し、その圧力が液体の飽和蒸気圧を下回ると、液体は常温でも沸騰し、無数の蒸気の泡が発生します。
- 破壊メカニズム: この泡は、液体の流れに乗って、羽根車内部の高圧領域へと運ばれます。すると、高圧によって泡は瞬時に押し潰されます。この泡の圧壊現象は、数千気圧にも達する極めて高い衝撃圧力を局所的に発生させます。
- 影響: この衝撃波が、何百万回と繰り返し羽根車に作用することで、あたかも金属が削り取られるように、羽根車表面に無数の孔食(ピット)が発生し、最終的にはポンプを破壊に至らしめます。また、激しい騒音や振動の原因ともなります。
このキャビテーションを防ぐためには、ポンプの設置位置や吸込配管の設計を適切に行い、ポンプが必要とする吸込圧力(有効吸込ヘッド)を確実に確保することが、工学的に極めて重要です。
まとめ
ポンプは、流体にエネルギーを与えるという、社会や産業の根幹を支える機械です。その選定と運用は、遠心ポンプが支配する「流量の世界」と、容積式ポンプが支配する「圧力の世界」という、それぞれの原理と特性を深く理解することから始まります。
そして、ポンプの性能曲線とシステムの抵抗曲線との対話を通じて最適な運転点を見出し、キャビテーションという破壊的な現象を回避するための流体力学的な配慮を行うことで、初めてその能力を最大限に、かつ安全に引き出すことができます。私たちの目に見えない配管の中で、黙々と流体を動かし続けるポンプは、まさに流体工学という科学技術の、最も身近で、最も重要な実践の場なのです。
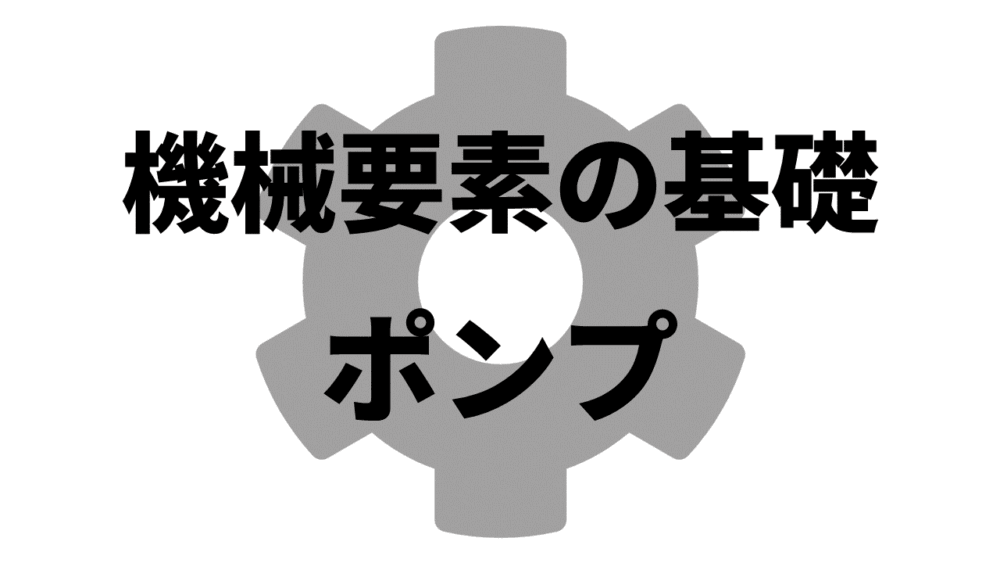
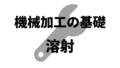
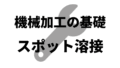
コメント